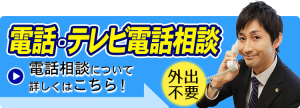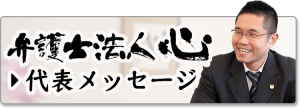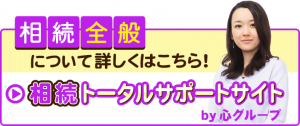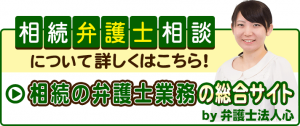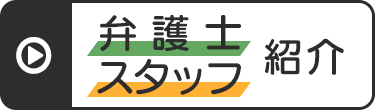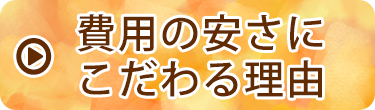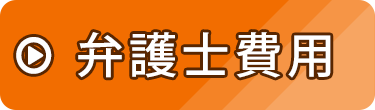相続放棄の必要書類
1 すべての案件で必要な書類
⑴ 被相続人の住民票除票または戸籍附票
相続放棄は、被相続人が死亡した時の住所地(相続が開始した地)を管轄する家庭裁判所の管轄に属します(家事事件手続法201条1項)。
これは、①相続の放棄に関する審判事件の判断に必要な資料は、被相続人の住所地に最も多く存在すると一般に考えられていること、②被相続人の住所地は明確で一義的に管轄裁判所が定まること、以上2点を理由とするものです。
そうなりますと、相続放棄の申述をある家庭裁判所に対して行う場合、その家庭裁判所に管轄権があることが分かる書類、すなわち被相続人の死亡時の住所地が分かる書類を提出する必要があるということになります。
これに該当する書類は被相続人の住民票除票または戸籍附票になりますので、相続放棄の際には、これらのうちいずれか1通を提出することになります。
⑵ 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続放棄は、死亡した被相続人に関する相続について行うものですので、その事実がわかる書類、すなわち被相続人の死亡が記載されている戸籍類の謄本を提出しなければなりません。
⑶ 相続放棄を行う方の戸籍謄本
相続放棄は、被相続人の相続人が行うものですので、被相続人の相続人であることを示す書類を提出しなければなりません。
相続放棄を行う方の戸籍謄本は、そのための書類として、相続放棄を行うすべての相続人が提出しなければなりません。
なお、相続人が被相続人の配偶者、または一度も婚姻したことのない子の場合は、上記⑵と⑶は同じ戸籍謄本となり、相続放棄の際に必要な書類も上記⑴~⑶のみとなります(⑵と⑶は同じですので、1通提出すれば十分です)。
他方、相続人が被相続人の子で、かつ婚姻により被相続人の戸籍から除籍されている場合は、上記1の⑵と⑶は異なる書類となりますので、それぞれ提出する必要があります。
2 相続人が兄弟姉妹の場合
最近は、相続人となった被相続人の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)からの相続放棄の相談が増えていますので、ここでは、相続人が兄弟姉妹のケースについて必要書類をご説明します。
まず、兄弟姉妹は第3順位の相続人となりますので、第1順位(被相続人の子)および第2順位(被相続人の直系尊属)の相続人がいないことが前提となりますが、ここでは、第1順位の相続人である子はもともといない、第2順位の直系尊属は被相続人の死亡よりも前に全員死亡している、というご相談の多いケースを前提に説明します。
まず、第1順位の相続人が存在しないことがわかる書類が必要になりますが、そのためには、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本を提出しなければなりません。
次に、直系尊属(被相続人の父母や祖父母等)の死亡の記載がある除籍等の謄本を準備します。
なお、直系尊属が相続人となる場合、被相続人から親等の近いものから順に相続人になりますが(つまり、被相続人の父母(養父母がいる場合は養父母も含みます)の両方または一方が被相続人死亡時に生存していた場合はその生存していた父母が相続人となり、父母の両方が死亡していた場合は、被相続人死亡時に生存していた祖父母が相続人になります)、死亡の記載がある除籍等の提出についてどこまで遡る必要があるのかについては、申述を行う家庭裁判所の運用によりますが、例えば、被相続人が80歳で死亡した場合は、直系尊属の死亡の記載がある除籍等については、どの家庭裁判所で申述を行うとしても、被相続人の父母のもののみで大丈夫でしょう。
3 戸籍類以外
相続放棄を行うためには、申述書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
申述書の書式は家庭裁判所の窓口で配布しており、また裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
つまり、3か月の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」という相続人の主観で決まることとなり、被相続人の死亡時(これは戸籍類により客観的に明らかです)から3か月以内に申述を行う場合は問題ないですが、死亡時から3か月を経過している場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を裏付けるための資料が必要になることがあります。
例えば、疎遠であった被相続人の債権者から相続人宛てに届いた督促状等です(督促状等の書面には通常、作成日等の日付が入っており、また、切手の消印にも日付が入っています。
書留等の場合は、郵便局のウェブサイトで配達日を調べることができ、その画面のプリントアウトを提出します)。
相続放棄で必要な書類は、単純なケースもありますが、複雑なケースもございますので、一度弁護士に相談いただくことをお勧めします。